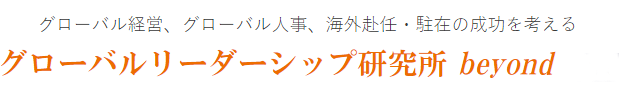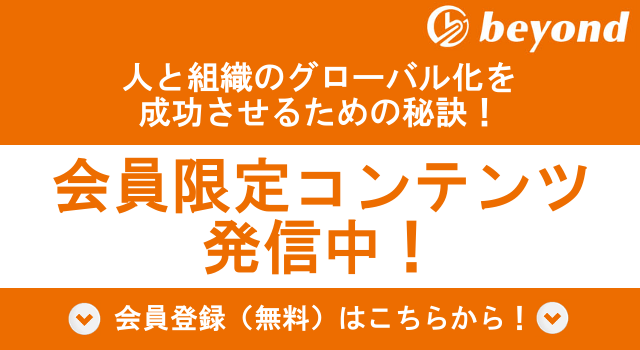日本の大企業は新興国で勝てない…
先進国の大企業が新興国市場で大きなシェアを獲得して成功するのは、なかなか難しいものです。日本でのマーケットシェアが大きな企業は、特にその傾向が強いように思います。日本での成功体験が社内での「正解」になってしまい、日本と新興国では違うことがたくさんあるにもかかわらず、現地市場に合った戦い方をすることができないことが、よくあります。つまり、成功体験が足枷になる、という問題です。
もう一つ厄介なことは、「安かろう悪かろう」問題です。新興国(≒途上国)市場では、商品・サービスの価格が先進国よりも低いのが一般的です。それゆえ、先進国企業としては、自国で展開している商品をスペックダウンして、あるいは、一昔前のモデルの商品を展開して、価格を下げようとしがちです。「ベトナムは、●●年前の日本」という言い方がされることも、この傾向を助長しているように思います。(更に言えば、日本とアジア諸国との歴史的な経緯によって堆積した自尊心(と、その裏側にある軽視)も大いに影響しているように思いますが、この文章では指摘するにとどめたいと思います。)果たして、日本市場とベトナム市場は、「進んでいる市場と遅れている市場」の関係なのか、単に、「違うだけ」の関係なのか。
リバース・イノベーション論が示唆してくれること
こういった点について考えるにあたって、「リバース・イノベーション」(ビジャイ・ゴビンダラジャン)を手に取ってみたいと思います。2012年に出版された本で、世界的ベストセラーになりました。日本語版の副題は、「新興国の名もない企業が世界市場を支配するとき」となっていますが、英語版の副題(”Create Far From Home, Win Everywhere”)の方が内容をストレートに示しているように思います。つまり、「(大企業が)本国から離れた場所でイノベーションを起こし、世界中で勝っていく」ということです。実際、書籍の冒頭で紹介されているGEのイメルトCEOの言葉は、「GEがアメリカで勝つためには、インドと中国で勝たなければならない」というものですし、本作のベースの1つになっている論文のタイトルは”How GE is Disrupting Itself”(GEは、いかにして、自らを破壊していっているのか?)というものです。
ちなみに、この本のヒットには、リバース・イノベーション、というネーミングの妙も少なからず貢献しているように思います。あまりスポットライトを当てられることが無い、というか、少なくとも、事業や出世のメインストリームとはなってこなかった途上国事業にスポットライトがあたり、しかも、そこでのイノベーションが、本国に還流(リバース)されてグループ全体に貢献する、というのですから、新興国事業担当者としても気持ちの良いものです。
 ただし、本作での定義としては、新興国で最初に採用されたイノベーションを全てリバース・イノベーションと呼んでいるので、必ずしも先進国側に還流することが必要条件というわけではありません。ですので、「新興国市場に適応したイノベーションを起こすには?」というテーマで、この議論を捉えるのが実践的だと思っています。
ただし、本作での定義としては、新興国で最初に採用されたイノベーションを全てリバース・イノベーションと呼んでいるので、必ずしも先進国側に還流することが必要条件というわけではありません。ですので、「新興国市場に適応したイノベーションを起こすには?」というテーマで、この議論を捉えるのが実践的だと思っています。
さて一例として、パソコン用ワイヤレスマウスの事例を紹介したいと思います。大いに簡略化して紹介しますので、詳しくは、ぜひ書籍を読んで頂きたいと思います。
アメリカに本拠を置くロジテックは、中国のワイヤレスマウス市場に参入しますが、当初は苦戦します。ワイヤレスマウスの性能を決める要素を大きく2つに分類すると、①内臓チップに関連する要素(受信距離、通信精度など)と、②形状に関する要素(表面、人間工学など)となります。ロジテックが想定していた商品群としては、ハイエンド品(①高②高)、ミドルエンド品(①中②中)、ローエンド品(①低②低)というものでした。アメリカに比べて、市場での価格帯が低い中国市場に対応するため、ミドルエンド品やローエンド品を投入していたのですが、どうにもシェアが上がらない。どうしたものか…
詳細な市場調査をしてみると、想定外のことが明らかになりました。アメリカと中国ではワイヤレスマウスに対するニーズが違っていたのです。1つには住宅環境。中国の都市部では集合住宅が多いので、アパートの隣の部屋とのマウス通信の干渉が大きな問題でした。それゆえ、通信精度に対する要求は高かったのです。また当時の中国では、パソコンをテレビに繋いで動画を視聴する、という行動が多かったそうです。そうなると、パソコンはテレビの横にあり、マウスはソファーに座るユーザーの手元にある。それゆえ、受信距離に対するニーズも高かったのです。結果として、①中~高②低、というスペックの組み合わせに対するニーズが大きかったのです。
先進国市場での目線で「安かろう悪かろう」の戦い方では、捉えることができなかった消費者のニーズです。現地市場を真っ新な眼で見つめたからこそ見出せた消費者ニーズです。
それでは、どのようにすれば新興国市場に適した商品を開発することができるようになるのでしょう。「リバース・イノベーション」の中では、いくつの重要ポイントと、開発やイノベーションを生む出すためのワークシートまで用意されています。ここでは、エッセンスを紹介したいと思います。
乱暴に一言で言ってしまえば、「新興国攻略用の特命チームを作り、思い切って権限を委譲せよ」ということです。
先ほどのワイヤレスマウスの事例も示唆している通り、本国や先進国市場で展開している商品のリストの中から、新興国市場に投入する商品を選んでいては、現地市場に評価されるものを展開できないということがあります。市場を真っ新な眼で見つめ、本当のニーズを捉えることが必要です。つまり、「現地に輸出」することでなくて、「現地で開発」することを意識すべきなのです。あるいは、「輸出」という言葉を使うのであれば、輸出すべきは、「商品」ではなくて、その商品を生み出してきた「技術・ノウハウ」「経営資源」である、という言い方ができると思います。
では、その「現地での開発」を実現するためには、どうするか。そのための専門部隊を現地に作れば良い、というのが、ゴビンダラジャンの主張です。この専門部隊は、あたかもベンチャー企業のように、柔軟かつスピーディーに市場研究と開発の活動を進めていきます。そういう存在ですから、社内の一般的な事業部のように、四半期や通年の損益やROIC(投下資本に対する利益の割合)などで評価されるのではなく、その開発活動の進捗によって評価されるべきです。また、開発の成果を出すために、その専門部隊には、一線級の人材を置き、思い切った権限委譲をしなければなりません。本国で展開している商品を「少しローカライズ」するというようなレベルではなく、真っ新な眼で市場を見つめ、新興国市場に適した商品・ビジネスモデルを開発しなければならないのですから、思い切った資源配分と権限委譲が必要になってくるわけです。…というのが、大まかな彼の主張です。
確かに、新興国に合った商品を開発しようとしても、そのプロセスにおいて本社側の関与や承認が大きすぎると、本国での「常識」が、現地市場に適した開発の妨げになることがあるでしょう。さらに日本企業では、日本での活動で成果を上げた人が経営層に上がっていくケースが多いので、経営陣が「日本事業での正解」を「グローバルでの正解」だと無意識に捉えがちです。加えて、経営陣が集団的な意思決定にするようであれば、日本起点の発言や後ろ向きな発言が新興国事業の裾を踏んで、問題は更に根深くなります。大きな企業全体が考え方をガラッと変える、というのはほぼ不可能なことですから、専門部隊として切り出す、というは有効です。また切り出したからには、社長が専門部隊という「異分子」を社内の外野の声から守る/守り切ることも必要になります。
人事については、現実問題としては新興国事業以外の事業もあるのでバランスが難しいところですが、思い切った任命は有効だと思います。人事は経営陣が社内外に強力なメッセージとなりますので、「これは、社長も本気なんだな」ということが伝わる人事が望ましいはずです。ところが、日本企業においてネックになるのが、年次の問題です。途上国という環境でエネルギッシュに活動できて、しかも、それなりの経験や知識を持っている、ということになると、いわゆる中堅の方がリーダー候補になるはずです。ただ、その年次の社員に、どこまでの権限を預けることが妥当なのか。「日本で言えば課長なので…」ということで判断してしまっては、本来の役割を達するのには不十分ということが多いでしょう。担うべき役割と権限は一致しているべきです。国際事業では、日本国内での年功序列を取っ払って考えることが必要な場面も多いでしょう。この点は、企業によって状況がかなり異なりますが…
なお、専門部隊を現地に放り込んだだけでは、新興国市場という大海に埋もれてしまうだけですので、本社の力を専門部隊の推進力に繋げる必要があります。本社との適度なコミュニケーションを維持して、権限を委譲された側は本社からの経営資源をしっかりと引っ張るように動くことも必要になります。
こういう風に見てくると、ここで言っている専門部隊というのは、一部の(多くの?)日本企業にあるような「海外部隊」とは全く別の存在であることが明らかになってきます。海外事業の売上構成が小さい企業には、「海外部隊」という位置づけの「海外に関する諸々は彼らにお任せ」というチームがあります。残念ながら、人員配置や権限は充実しておらず、にもかかわらず、雑務も含め業務は増えていく。社内の(メインストリームであるところの)国内事業部隊からの協力は得られずに、コミュニケーションも薄い。これでは、新興国市場に合ったイノベーションを実現することは不可能でしょう。
辺境より起こる変革
「変革は辺境より起こる」という言葉があります。日本の歴史を見ても、鎌倉や江戸はもともと未開の地でしたし、明治時代の開化を牽引したのも「地方」の人々でした。そういう意味では、先進国企業にとって「辺境」である新興国においてイノベーションが起こり、本国も含むグループ全体に波及する、というのは、極めて自然なこととも言えます。
辺境で変革を起こし、全体に波及させていくためには、経営者の思い切った専門部隊の組成と権限委譲が必要になります。「これからはアジアの時代だ!」「アジアをやるんだ!」と息巻いておきながら、資源や権限の配分の様子を傍から見ると全く本気に見えない、ということの なんと多いことか。社長の(地理的&時間的な)視野と覚悟が、新興国市場での成功の鍵を握っています。
小川 達大
Latest posts by 小川 達大 (see all)
- アジア経営論考(5)大企業が新興国で戦うには? ~意志ある異分子を変革の中心に~ - 2017年2月23日
- アジア経営論考(4)地域戦略の「塔」構造~東南アジアでの戦略づくり~ - 2016年12月21日